
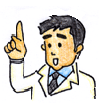
 |
インフルエンザ/ワクチンQ&A(詳細解説)
|
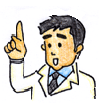 |
注意!当院は乳幼児の診察を行っていないため、乳幼児のインフルエンザの話はかなり省略しています。
公開日2002.10.01 更新日 2004.12.08 更新履歴 HOMEへ(メニューを表示) メニューを隠す
記事はあくまでも参考に留め、治療方針は診療医師と相談してください。
インフルエンザ流行状況
、各地の発生状況、各県のABタイプ別発生状2005.02.10リンク確認
A:かえって害になる可能性が高いので、やめましょう。インフルエンザ流行期に、高熱がでたらぜひ診察を受けましょう。
インフルエンザになった小児にアセトアミノフェン以外の解熱剤(非ステロイド抗炎症剤:アスピリン、メフェナム酸、ジクロフェナックなど)を使うと死亡率が著しく高くなることが判明しました(ライ症候群などと呼ばれています)。小児で特に多いとあるのですが、15歳以上でも全くないわけではないので注意ください。
総合感冒薬には、鎮痛解熱剤以外にも、咳止め、痰の切れをよくする薬、鼻水を止める薬(抗ヒスタミン剤)が含まれています。これらも、急性ウイルス性熱性呼吸器疾患にはかえって害になるとされています。したがって、いわゆる感冒剤は適切でないと言えます(参考Q2)。
A:特に、小児ではアセトアミノフェン(商品名:アンヒバ座薬、アルビニー座薬、カロナールなど)以外は、厳重に慎むべきです。水分の補給と物理的に冷やすことを勧めます。
解熱剤ではインフルエンザのときは使用を避けなければならないものがあります。特に小児では、使用禁止の解熱剤が多数あります。例えば、アスピリンを15歳未満のインフルエンザの患者さんへ投与すると、脳障害や重篤な全身症状で生命の危険すら生じる場合があります。アスピリン以外の解熱剤もアセトアミノフェン以外は安全とは言えません。
また、15歳以上の患者さんであっても、インフルエンザに脳炎・脳症を併発した場合、それを悪化させる可能性があります。市販の鎮痛解熱剤の多くは、15歳未満の子供のインフルエンザには使ってはいけません。例外的に、アセトアミノフェンは15歳未満に使っても、安全とされています。
米国ではアスピリンが使われていた時はライ症候群が多数みられましたが、急性ウイルス性熱性呼吸器疾患へのアスピリン使用を中止した後は、ライ症候群はなくなりました。2001年に厚生省も小児の急性発熱疾患へのアセトアミノフェン以外の鎮痛解熱剤の使用を制限しました。
基本的に発熱は病原体から身体を守る防御機能ですので、むやみと下げてはいけないのです。特にインフルエンザでは危険です。発熱がある場合には、物理的に冷やしたり、水分・電解質、栄養を十分に補給し、安静を保持するように勧めます。
厚生労働省発表資料
「インフルエンザによる発熱に対して使用する解熱剤について」(平成13年5月30日)
A:身体の休養が基本。また、ウイルスが全身に広がるのを防ぐ薬で早く治るようになりました。
・早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。インフルエンザ治療薬は、発症から遅れると効果がありません。
・安静にして、休養をとりましょう。特に睡眠を十分にとることが大切です。
・水分を十分に補給しましょう。ポカリを1/2に薄めたものがお勧めです。水やウーロン茶でも結構です。
ただし、下痢・嘔吐があるときには緑茶、柑橘類のジュース、炭酸飲料水など刺激性のあるものは、症状を悪化させやすいので避けましょう。
・1998年11月から抗インフルエンザウイルス治療薬が使用ができるようになりました。また、インフルエンザにかかったことにより、他の細菌にも感染しやすくなりますが、このような細菌の混合感染による肺炎、気管支炎などの合併症に対する治療として抗生物質が使用されます。
なお、市販のかぜ薬は発熱や鼻汁、鼻づまりなどの症状をやわらげることはできますが、インフルエンザウイルスや細菌への直接効果はありません。むしろ、風邪薬に含まれる鎮痛解熱剤は、小児では重篤な薬害を引き起こしやすいと言われ、使用禁止になっている薬が多いので注意しましょう。
A:「アマンタジン(商品名シンメトレル)内服薬」、「ザナミビル(商品名リレンザ)吸入薬」、「オセルタミビル(商品名タミフル)内服薬」などよく効く薬があります。
日本では1998年に「アマンタジン」がインフルエンザ治療薬として認可されました。ただし、A型のみにしか効果はありません。米国では重症化のおそれがあるとされるグループやワクチンの接種が出来ない者、医療従事者へのワクチン接種を補う予防薬としての使えます。
しかし、我が国では抗ウイルス剤としての使用経験が少なく、また、アマンタジンを投与された患者の約30%でアマンタジン耐性のA型インフルエンザウイルスが出現するという報告もあることから安易な使用は慎むべきです。
副作用としては、主として嘔気などの消化器症状やふらつき、不眠などの中枢神経症状が軽度ながら出現することがあると報告され、使用した場合の注意事項としては、車の運転を避けることなどが挙げられています。
2001年にインフルエンザウイルスが細胞から細胞へ感染・伝播することを阻害する抗インフルエンザウイルス剤「ザナミビル(吸入薬)」と「オセルタミビル(内服薬)」が保険適応になりました。これらはインフルエンザA、Bの両方に有効です。副作用もあまりありません。
3剤とも発症後48時間以内に服用しないと効果がありません。また、できるだけ病気の初期に治療を開始した方が、効果が期待できますので、24時間以内に診察を受けることを勧めます。
これらの薬剤には病気の経過を短縮する効果は認められていますが、ワクチンのように死亡や重症肺炎を防ぐことまでは期待できず、ワクチンの代わりになるものではありません。
ワクチンと併用では、薬剤の効果が強まり、翌日に解熱する割合が増加します(相乗作用といいます)。また、ザナビルとオセルタミビルはアマンタジンのように薬剤耐性ウイルスの出現が少なく、たとえ耐性ウイルスが現れてもその感染力は低くなります。
いずれの薬剤も服薬開始の翌日には劇的に解熱することが多いのですが、薬をすぐに中止すると再発することもあり、3〜5日は続けることを勧めます。受験生などに予防薬としても有効ですが、この場合には健康保険は使えません。
なお、乳幼児への使用はA型インフルエンザにしか効果のないアマンタジンしか認められていませんでしたが、2002年7月には「タミフルドライシロップ3%」が発売されました。
● ザナミビル(商品名:リレンザ)の使用方法
ザナミビルは吸入粉末剤です。1回に5mgを2回吸入(計10mg)を12時間毎に1日2回、4-5日間続けます。ザナミビルで1秒率の低下や一部で喘息発作が生じると報告があり、呼吸器基礎疾患のある患者には勧められません。喘息の人は他剤を使うか、注意して使う必要があります。
ザナミビルの吸収は少なく、吸収されたものは急速に尿に排泄されます。吸収されなかったものは便に排泄されます。腎不全に人に使った際のデータはありませんが、高用量での経験から、腎不全でも高齢者でも減量する必要はないと考えられます。肝疾患に関する成績はありません。
12歳以上が保険適応で、12歳未満では認可されていませんが、治験では5〜12歳で成人同様に有用で、副作用も変わりなかったといいます。
● オセルタミビル(商品名:タミフル)の使用方法
タミフル(75)カプセルは1回1capを1日2回、4〜5日間続ける。薬剤添付書類には5日間続けるようになっていますが、「4日でも再発はない」との経験的報告もあります。頻度の多い副作用は吐き気(3.9%)、下痢(5.5%)、腹痛(6.8%)です。
消化器症状は服用直後に出現、服用を続けても1〜2日で症状は消失することが多いとされてます。腎機能障害患者は1cap/日に減量するか、他剤を選ぶようにします。37.5Kg以上の小児では、大人と同じ内服量でよいとされています。
「タミフルドライシロップ3%」が2002年7月から発売開始されました。
用法・用量: 通常、幼小児にはオセルタミビルとして、小児から大人まで、1回2mg/kg(ドライシロップ剤として66.7mg/kg)を1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与します。ただし、1回最高用量はオセルタミビルとして75mgとする。適応は1歳以上で体重8.1Kg以上となっています(※注1)。
※注1:使用上の注意で、
「1歳未満の患児(低出生体重児、新生児、乳児)に対する安全性は確立していない」
「臨床試験において、体重8.1kg未満の幼少児に対する使用経験はない」とある。
参考資料:【インフルエンザ最新情報】:Q4:1歳未満児にタミフルは使ってよいか
2004.12.08追加
● リレンザとタミフルの使い分け
上記の特徴を考えながら使い分けしますが、実際の適応対象者はほとんど同じになります。吸入剤という特殊性のために、国内外とも使用頻度でタミフルが大きくリードしています。
●アマンタジン(商品名:シンメトレル) 一日50mgを2錠 朝昼または朝夕の2回に分け内服、最長5日まで。
(寝付きが悪くなるので夕方ではなく、昼の内服がよいが、初日は早期の効果を期待して昼、夕とします。)
アマンタジンは1966年に米国で抗インフルエンザ薬として開発されましたが、むしろ日本ではパーキンソン病の薬として使われてきました。1998年にはA型インフルエンザ治療薬としての処方が認可されました。アマンタジンはA型インフルエンザウイルスの増殖を抑えます。
主な利点としては、
○A型インフルエンザの治療薬として有効(新型のインフルエンザウイルスにも有効)。
○服用後24時間以内に効果が出る(病気の初期ほど良く効く.有効率は約60〜70%)。
○ワクチンと併用で相乗作用が期待できる。
○ 一時的な予防薬としても有効。
などがあります。
欠点としては
×発熱後48時間以上経過した場合は効果が期待しにくい
×B型のインフルエンザには効果がない。
×脳へ薬が移行するために、精神・神経症状の副作用が出ることがある。
不眠、眠気、集中力低下、ふらつき、抑うつ、手のふるえ、歩行障害、食欲低下、吐き気などが数%程度。
とくに喘息治療薬のテオフィリン(点滴、テオドール、ユニフィルなど)の併用で痙攣が生じやすい。
×長期使うと耐性が生じやすいので、内服は4〜5日とする。(耐性ウイルスの出現頻度は30%)。
などがあります。
| 抗インフルエンザ薬の比較(2001.3月現在)Medical Digest 2003 Jan vol 52 p52 松本慶蔵 長崎大学名誉教授より、極一部変更 | |||
| シンメトレル | リレンザ | タミフル | |
| 認可日 | 1998年11月再認可 | 2001年2月保険採用 | 2001年2月保険採用 |
| 有効ウイルス | A型 | A型、B型両方 | A型、B型両方 |
| 剤形、投与量 | 経口100mg/日 | 吸入1回10mg 1日2回 | 経口(プロドラッグ)75mg 1日2回 |
| 日数 | 標準5日間 | 標準5日間 | 標準5日間 |
| 作用機序 | M2タンパク阻害(脱殻阻止) | ノイラミニダーゼ阻害剤 | ノイラミニダーゼ阻害剤 |
| 作用部位 | 感染細胞内でウイルスファゴゾームのpH低下抑える | 感染細胞より増殖ウイルスの遊離阻害、薬剤は直接感染部位へ、MICの500〜1000倍以上分布 | 感染細胞より増殖ウイルスの遊離阻害、薬剤は血中より(80%の生体利用率)MICの200倍到達 |
| 下気道移行 | 吸入量の約15%(気管・気管支・肺) | 良好(BALFにて証明) | |
| 血中半減期 | 約16時間 | 約2〜3時間 | 約8時間 |
| 中耳・副鼻腔移行 | 良(?) | ? | 良好 |
| 排泄 | 腎 | 大半は気道分泌物→胃腸、血中に移行した分は腎(未変化体) | 腎(活性未変化体) |
| 副作用 | 不眠、ふらつき、まれに不整脈、けいれん | ほとんどない(気管支喘息には慎重に) | 嘔気、嘔吐が数%あるが軽度、食後服用で消失 |
| 耐性ウイルス | 生じやすい。病原伝搬性は感受性ウイルスと同じ。耐性は翌年の流行時までは持続しない。 | ほとんど0に近い | 1〜5%(ただし、病原性極めて弱い、他人に感染できないとある) ※追加新情報:2004年4月6日、子どもに使うと、約3割に耐性ウイルスが出現することが報告された。 |
| 予防効果 | あり | あり | あり |
| 小児での有効性* | あり | あり(4歳以上) | あり(1歳以上) |
| 現在承認国 | 世界的 | 欧州、米国、日本 | 米国、カナダ、スイス、日本 |
| *日本では小児にはオセルタミビルのみ承認されている。 | |||
※追加新情報
東大医科学研究所の河岡義裕教授らは、タミフルを子どもに使うと、約3割に薬の効きにくい耐性ウイルスが出現すると、2004年4月6日の日本感染症学会で報告した。
A型インフルエンザに感染した14歳以下の子ども33人を対象に、オセルタミビルを3―5日間投与し、治療前と治療後のウイルスの変化を調べた。
その結果、33人中9人は治療後、ウイルスの構造が変化し、薬が効きにくくなっていた。耐性ウイルスは、治療を始めて4―8日後に出現していた。ただし、耐性ウイルスがどの程度の病原性を持つかなどはわかっていない。
これまでオセルタミビルの耐性の出現率は子どもで5%程度と考えられていたが、河岡教授は「今回の研究は3歳以下の子どもが多く、インフルエンザに生まれて初めて感染した場合、ウイルスが増殖する期間が長く、耐性が出やすくなった可能性がある」としている。
参考:【最新情報】:Q5:タミフル耐性ウイルスは? 2004.12.08追加
2004.12.08追加修正
A:学校保健法ではインフルエンザでの出席停止期間が解熱後2日間です。
小児ではインフルエンザウイルスは咽頭から発病後4〜5日、長いと1週間程度検出されます。インフルエンザ治療薬を投与することによりウイルス排泄期間が短縮するかどうかは明らかにされていません。抗ウイルス薬の使用の有無にかかわらず、ウイルスの排泄は4〜5日程度と考えられるので、周囲への感染を考えた場合、登校は解熱後3日目以後を目安にすればよいと思われます。
2004年の日経メディカル11月号の記事では、38度以下に解熱した日を0日目としたとき、翌日はウイルス残存率約80%、2日目で約40%、3日目で約10%でした。
類似:【最新情報】:Q6:タミフル内服解熱後は登校してよいか?
2004.12.08修正
A:インフルエンザAに対しては、シンメトレルとオセルタミビルは効果がほぼ同じ。価格はシンメトレルが格段に安い。
インフルエンザ治療薬として、●シンメトレル(商品名:アマンタジン、アマゾロンなど)と●ザナミビル(商品名:リレンザ)、●オセルタミビル(商品名:タミフル)がある。シンメトレルはA型インフルエンザには効果があるが、B型インフルエンザには無効である。ザナミビルとオセルタミビルはA型,B型の両方のインフルエンザに有効だが、ザナミビルは内服薬がなく、吸入薬のみである。以上の理由でオセルタミビルが多く処方されている。
しかし、効果や価格を考慮するとA型インフルエンザではシンメトレルがお勧めである。
2003年の医療情報新聞、雑誌に書かれている臨床実地家の評価をみると「シンメトレルの効果はオセルタミビルとほぼ同等」という。
一方、標準的な5日処方(または4日処方)でかかる薬剤費を比較してみると、オセルタミビルの755.4円(一日薬価)×5日=3877円に対して、アマンタジン(シンメトレル)の79.2円(一日薬価)×5日=396円、後発品のアマゾロン(シンメトレル)ならさらに安く、19.8円(一日薬価)×5日=99円である。なお、内服期間に関しては5日でなく、4日でよいという意見が少なくない。当院でも原則4日分を処方している。シンメトレルは耐性ウイルスが生じやすいことが問題になりそうだが、現在のところ問題になっていない。
以上の理由から、A型インフルエンザ治療薬としては、効果が同等、価格が1/10〜1/40となるシンメトレルがお勧めと言えるようです。
なお、健康保険上は問題になるが、A型インフルエンザではシンメトレルとオセルタミビルの併用は、単独よりも効果が高いとの報告がある。
|
商品名
|
薬品名
|
1日薬価
|
5日分の価格
|
3割負担
|
支払い料金差額
|
|
|
タミフル
|
オセルタミビル
|
755.4円
|
3877円
|
1163円
|
1133.3円
|
|
|
アマンタジン
|
シンメトレル
|
79.2円
|
396円
|
118.8円
|
87.1円
|
|
|
アマゾロン
|
シンメトレル
|
19.8円
|
99円
|
29.7円
|
0円
|
2003.12.05追加 2003.12.10更新
A:朝日メディカル2004.1月号のインフルエンザ特集から、まとめました。
小児に対するタミフルの使用経験では、
●発病後2日以内の投与では、翌日に44%、2日後に86%が解熱した。
●発病初日でも2日目でも投薬から解熱までの期間に差がなかったので、投薬開始が早いほど全有熱期間は短くなった。
● 年少児と年長児で有熱期間に差がなかった。
● 90%は抗生剤なしで解熱した。
● 投与終了時(投与4日後)には90%が解熱していたにもかかわらず、50%以上からウイルスが検出された(小児感染症学会2003)
● タミフル3日投与で再熱発率は4.2%と低かった(八宮ら 小児感染症学会2003)
● 保険では認められていないが、アマンタジン(シンメトレルなど)とオセルタミビル(タミフル)の予防的投与が米国では認められている(発病防止効果50-90%)。
● ハイリスクの小児入院患者で、タミフルを予防投与行い、非常に効果があった(新庄ら 小児感染症学会2003)。
参考 Medical ASAHI 2004.1月 三田村 敬子(川崎市立川崎病院小児科)著
2004.01.23記