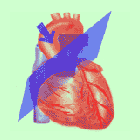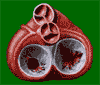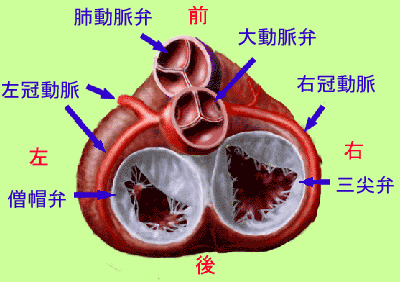心臓の横断面-心房と心室の境界の横断面
解説
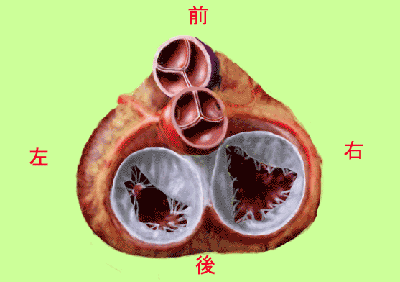
左の図は、上図ような心臓断面を矢印の方向(頭側)から見た断面図である。4つの心臓弁が同時に観察できる。本来なら僧帽弁(そうぼうべん)と三尖弁(さんせんべん)の頭側には、それぞれ左房と右房がある。
1)肺動脈弁(はいどうみゃくべん)
右室と肺動脈の境にある弁。
肺動脈の血圧は20-30mmHgぐらいしかなく、この弁の閉鎖不全が、臨床上問題になることは滅多にない。肺動脈弁狭窄症は先天性であり、後天性はほとんどない。
2)大動脈弁(だいどうみゃくべん)
左室と大動脈の境にある弁。
血液が大動脈から左室に逆流しないように働く。左室の収縮期(左室が小さくなる時)に弁は開き、血液を送り出した後には弁は閉鎖する。
●左右の心室の入り口の弁(房室弁)●
3)僧帽弁(そうぼうべん)
左室と左房の間にある弁。僧帽弁狭窄症は高齢者を除き、日本ではめったに見られなくなった。原因となるリウマチ熱によるリウマチ性弁膜症がほとんどなくなったからである。
僧帽弁閉鎖不全症はいろいろな原因でおこる。ある程度以上の閉鎖不全症では手術以外に根本的な治療法はない。
4)三尖弁(さんせんべん)
右室と右房の間にある弁。三尖弁の 狭窄や閉鎖不全が単独で生じることは少なく、僧帽弁膜症や心房細動に合併することが多い。右室や三尖弁輪拡大によって生じる。急速に進んだ心不全により心拡大が生じると三尖弁閉鎖不全症になりやすい。急に生じた三尖弁閉鎖不全症は、心不全の改善によって、心拡大が改善されると弁逆流が著明に減少する。
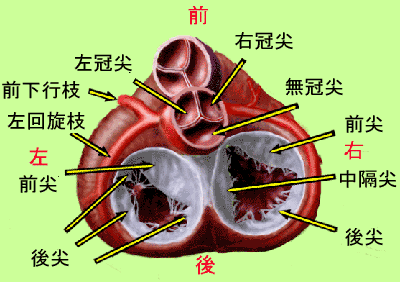
肺動脈弁は臨床上問題になることが少ないので、省略した。
1)大動脈弁弁尖
大動脈弁は3つの弁尖からなる。そのうち2つの弁尖に繋がる大動脈はやや外側にふくれており、そこから心臓の筋肉を栄養する冠動脈が分岐している。右冠動脈と左冠動脈がそれである。右冠状動脈、左冠状動脈とも呼ぶ。大動脈弁の弁尖は通常3つだが、先天的に2つしかない大動脈2尖弁は中年期の大動脈弁弁膜症の原因となる。
2)僧帽弁弁尖
前方(胸壁側)にある大きな前尖と後方(背側)にある短い後尖からなる。2つの乳頭筋と腱索という繊維性の紐で支持されている。この紐が長くなってゆるんだり、切れたりすると弁の閉鎖不全が生じる。
3)三尖弁弁尖
3つの弁尖から成る。