
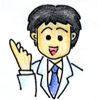
 |
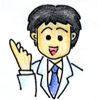 |
|
甲状腺の病気に関しては当院の解説よりも詳しいものが、ネット上でたくさんあります。そちらも参考にしてください。
01)甲状腺機能亢進症とはどんな病気ですか?
02)甲状腺機能亢進症の症状と所見は?
03)どんな検査がありますか?
04)どんな治療方法がありますか?
05)治療薬の副作用は大丈夫ですか?
06)治療中の注意点は?
07)薬はいつまで続けるのですか?
08) 妊娠しているときの甲状腺機能亢進症の治療の注意点?
09)バセドウ氏病と間違いやすい病気がありますか?
10)どんな時に甲状腺の専門家に紹介するのですか?
11)甲状腺の手術適応
参考資料
・medical practice 2002年2月号 甲状腺疾患 ●エビデンスに基づいた日常診療
・ medicina 2002.8月号 内分泌疾患の拾い上げとマネジメント39:1276-1279 高須 信行
A:甲状腺ホルモンが多すぎるため、いろいろな異常がでる病気です。代表的な病気としてバセドウ氏病があります。
甲状腺機能亢進症は甲状腺から甲状腺ホルモンがたくさん出過ぎるため、全身の細胞の新陳代謝が異常に高まる病気です。
正常では、甲状腺ホルモンの量は脳下垂体という脳の一部からでる甲状腺刺激ホルモン(TSH)という別のホルモンの量で調整され、甲状腺ホルモンが適度な量になるようにコントロールされています。
つまり、甲状腺のホルモンが不足と判断されれば、甲状腺刺激ホルモンが血液にたくさんでて(TSH増加)甲状腺へ達し、「甲状腺ホルモンをもっとたくさん製造しなさい」と甲状腺への命令を出します。
逆に、甲状腺ホルモンが多すぎると判断されれば、血液中に放出される甲状腺刺激ホルモンが減少し(TSH減少)、「甲状腺ホルモンの製造をゆっくりしなさい」と甲状腺への命令を出します。
しかし、ここで偽りの「もっと製造しなさい」との偽の命令書がでるとどうなるでしょう。 甲状腺から過剰のホルモンが造り続けられることになります。 この「偽の命令書」の働きをするのが、甲状腺受容体抗体(TBII,
TRAb)という病的なタンパクです。
ほとんどの甲状腺機能亢進症は、甲状腺細胞の表面にある甲状腺ホルモン受容体という部分に対する抗体(甲状腺受容体抗体)というものができることによって起こる「自己免疫疾患(※注)」であることがわかっています。
そして、この病気の発見者の名前から「バセドウ氏病」と言われています。 バセドウ氏病は男女比1:5で、女性に多い病気です。発病は20〜40歳代に多いとされてます。
(※注):自己免疫疾患とは: 本来、免疫は外部からきたウイルスや細菌などの異物や老朽化や傷んだ細胞を、「自分ではないもの(非自己)」として、認識して攻撃、処理します。 これにより、我々の身体は「正常な細胞の集まりとしての生命」が維持できるのです。 ところが、正常な細胞や身体の一部を、「非自己」と誤認して、これを攻撃するためにおこる病気のグループがあります。 これを「自己免疫疾患」と呼びます。
2003.2.1記
A:甲状腺の腫れ(首の腫れ)と特徴的な症状があります。
【症状】
動悸(心臓がどきどきする)、頻拍(心拍数が多い)、汗かき、湿った皮膚、たくさん食べるのにやせる、手の指が震える、疲れ易い、暑がり、イライラして落ち着きがない、軟便・下痢傾向、不眠症などがあります。月経過少、無月経にもなりやすい。
頻脈が続くと、脈が乱れ、さらに心不全を起こすことがあります。 また、眼球突出や眼光が鋭くなるなどは有名な症状です。 骨粗鬆症にもなりやすくなります。
男性では約10%に、「繰り返す手足の一時的な麻痺(周期性四肢麻痺)」がでます。
【所見】
ほとんど場合に甲状腺は腫れて大きくなります。 ただし、腫れの程度と病気の重症度は必ずしも関係がありません。
また、症状が強くでる人と余りでない人があります。頻脈(脈が速くなる)、心房細動などの不整脈もみられます。
若い人の甲状腺機能亢進症は、●動悸、●甲状腺の腫れ、●眼球突出の3つの特徴がそろっていることが多く、診断は難しくありません。
しかし、高齢者の甲状腺機能亢進症は体重減少のみが目立ち、動悸や眼球突出などが目立ちにくく、診断が困難になります。
医師はこのことを配慮する必要があります。
2003.2.1記
A:甲状腺機能亢進症かどうかの検査と、さらに詳しく病気の状態を調べる検査があります。
【血液検査】
・血液中の甲状腺ホルモンが高値とTSHの極端な低下。
・ TSH受容体抗体や異常甲状腺刺激物質が陽性。
また、総コレステロールの低下もみられます。 バセドウ氏病が疑われる場合には、TSH受容体抗体の測定を行います。
測定の方法にはTBII(TSH binding inhibiting immunoglobulin:甲状腺刺激ホルモンの結合を阻害する活性を測る方法)とTSAb(thyroid
stimulating antibody:甲状腺を刺激する活性で測る方法)とがあります。 前者は甲状腺機能亢進の程度と関係が深く、後者は眼球突出症との関係が深いと言われています。
バセドウ氏病の診断をつける場合には、TBII(一般にはTRAbと呼ばれる)を最初に測った方がよいようです。 これにより、バセドウ病の診断がつくばかりでなく、この数値が高いと治りにくいと予想されます。
TBIIが陰性の場合にはTSAbを測定して、バセドウ氏病の診断をつけます。 TSH受容体抗体が30%以上の甲状腺機能亢進症は、バセドウ氏病と考えて治療を開始します。
注:びまん性の甲状腺腫 + 甲状腺ホルモン高値の約10%がバセドウ氏病でなく、無痛性甲状腺炎と言われています。
(medical practice 2002年2月号 大阪福祉事業財団すみれ病院 浜田 昇談) 2003.2.1記
A:通常は抗甲状腺薬と呼ばれる内服薬で甲状腺の働きを抑制します。そして、病気が落ち着くまで、何年も治療を続けます。
治療には3つの方法があり、それぞれに長所と短所があります。
【内服療法】
最も行われている標準的な治療方法です。 甲状腺の働きを抑える●メルカゾールや●プロパジール(またはチウラジール)を内服します。
ともに甲状腺のホルモン合成に大切な酵素を邪魔して、甲状腺ホルモンの合成を阻害します。前者は後者よりも作用が強い薬剤です。
授乳・妊娠時などを除いて、メルカゾールを使うことが多いようです。
最初は多めに薬を使い、ホルモンのバランスを見ながら薬を減らしてゆきます。
メルカゾールなら3〜6錠(15〜30mg)、プロパジールなら6錠(300mg)から開始します。
甲状腺ホルモンが正常化したあとに、徐々に薬の量を減らし、甲状腺ホルモンが正常範囲内に維持できる量にします。
なお、TSHは遅れて正常化するので、抗甲状腺薬の減量の指標には使いにくいとされてます。
減量が遅れると強い甲状腺機能低下症となり、甲状腺腫の増大の原因となります。 維持量はメルカゾールなら通常1〜2錠/日です。
ホルモンが正常化してもすぐに薬を中止すれば、ほとんどの場合再発します。 日本の成績からは2〜3年は薬を続けることがほとんどです。根気よく薬を続けなければなりません。
この治療の長所は、薬を飲むだけなので簡単なことと、比較的お金がかからないことです。 短所は、時間がかかること、ときどき薬の副作用で、じんましんや白血球が減ってしまう副作用がでることです。
もし、白血球が減ってしまう副作用がでた場合は、扁桃腺炎を起こして喉が痛んだり、高熱がでたりします。
その様な症状が現れたら、直ちに服薬を中止して病院で血液検査を受け、白血球の数を調べる必要があります。 早期に対処すればよくなります。
【外科療法】
大きく腫れた甲状腺を切って小さくする手術です。
手術をする前には、まず飲み薬で甲状腺ホルモンを正常化しておく必要があります。その後で、全身麻酔を行い手術します。
この治療の長所は、治療にかかる時間が短いことと治療後の再発が比較的少ないことです。 短所は、傷跡が残ること(美容上の問題)、切除する範囲が小さいと再発してしまうこと、入院しなければならないことです。
【放射性ヨード内服療法(RI療法)】
日本ではあまり行われていません。
放射性ヨードをカプセルに入れて飲んで、大きくなりすぎた甲状腺を放射線で破壊する治療です。
外来で治療できますが、治療中に妊娠する可能性のある女性には使えません。治療後の将来の妊娠には問題ないとされています。
中高齢の方の治療に使われることがありますが、放射線科の大きい施設があるところでないと薬が処方できないことになっています。 放射線による副作用や癌の発生の危険性などはないとされています。
この治療の長所は、薬のアレルギーなどがあって、内服療法ができない人でも治療ができることが一番です。 早く病状がよくなるため、早期に抗甲状腺剤が中止できます。
短所は、できる病院が限られていることと、若い人には使えないことです。 甲状腺機能低下症になってしまうので、甲状腺ホルモンを一生補充する必要がでてきます。
2003.2.6記
A:抗甲状腺薬は皮疹や肝臓障害、さらに重篤な「白血球減少」などが起こりやすいので注意が必要です。
最も注意すべきは、「白血球が少なくなる無顆粒球症」です。定期的な血液検査などで注意する必要があります。
ほかによくおこる副作用は「じんましん」や「肝臓障害」です。
もし、白血球が減ってしまう副作用がでた場合は、扁桃腺炎を起こして喉が痛んだり、高熱がでたりします。
その様な症状が現れたら、直ちに服薬を中止して病院で血液検査を受け、白血球の数を調べる必要があります。 早期に対処すればよくなります。
2003.2.6記
A:以下解説します。
○甲状腺疾患の検査
ホルモンのバランスを調整するために、病状に応じて1週間〜3ヶ月おきに血液検査が必要です。
薬の副作用がでていないかどうかを調べるためにも必要です。
その他に、甲状腺超音波、レントゲン検査、シンチグラフィーなどの検査を必要に応じて行います。
○甲状腺疾患療養のポイント
初期の症状が強い時期の安静を除いて、特別な注意は必要はありません。
ただし、喫煙があると再発率が高くなり、眼の症状によくないので禁煙とします。
2003.2.1記
A:検査をみながら減量し、やめることを考えます。
1)TRAb(TSAb)が陰性化、2)一年以上甲状腺機能が正常、3)甲状腺腫が大きくない(長径6cm未満)など参考にします。
標準的な治療経過では、最初はメルカゾールなら一日3〜6錠から開始すると、甲状腺ホルモン(FT3、FT4)は数ヶ月後に正常化します。
甲状腺ホルモン(FT4)と甲状腺刺激ホルモン(TSH) の2つともが正常範囲になるように薬の量を調整します。
抗甲状腺薬が一日一錠になったら、薬を中止してよいか考えます。 中止できるかどうかの判断で役立つのがTSH受容体抗体です。
TSH受容体抗体が陰性にならないと、薬を中止しても再び症状が悪化するので、陰性になるまでは薬を続けます。
TSH受容体抗体が陰性の場合は、中止すると75%は再発がありませんが、25%は再発します。 いきなり中止するよりは、一日おきに一錠を6ヶ月間続けるという風に徐々に薬を減らしてゆくのがよいとされています。
ただし、バセドウ氏病になりやすいと言う体質そのものは残っているので、何かをきっかけに再発することがあることを覚えておく必要があります。 分娩後、アレルギー性鼻炎の後は再発が多いとされています。また、喫煙者は緩解率が低いとされています。
また、再発は一年以内が多いとされています。
2003.2.1記
A:妊娠初期の軽度の甲状腺機能亢進症は治療の必要がないことが多い。
抗甲状腺薬は妊娠・授乳中も勝手に薬を中止するとよくありません
●一時的な軽度の甲状腺機能亢進症といわれた人の場合
妊娠初期(8〜13週)は絨毛性ゴナドトロピンが甲状腺を刺激することにより、軽度の甲状腺機能亢進症になることがあります。
これは妊娠中期には正常化する一時的な異常で治療の必要がありません。
●すでに抗甲状腺薬を飲んでいる人の場合
抗甲状腺薬は妊娠・分娩にも基本的には問題ありません。勝手に薬を中止することの方がよくありません。
ただし、治療薬(メルカゾール)によっては胎児や乳児への影響がでやすいので、薬の種類を変えることがあります。
妊娠中はプロピルチオウラシル(商品名:プロパジール)の方が望ましいと考えられています。
授乳中も母乳への薬の移行が少なく、常用量では乳児の甲状腺機能には影響しないプロピルチオウラシルの方がお勧めです。
1)食事は、検査の前などに特別にヨード制限食とすることがありますが、日常の生活では特に制限はありません。 海苔や海産物を好んで多食したり、逆に極端に制限するとかえって病状を悪くすることがあります。
2)処方された薬は副作用がでない限り、根気よく続けて下さい。 病気の症状も薬をのめば半月から1ヶ月で消えてしまいますが、ここで治ったと思って薬をやめると再発します。 こうして再発をすると2回目以後の薬の効き目が落ちるといわれています。
3)規則正しい生活をして、適度な運動と適度な休養をってください。 特に、妊娠をきっかけに病気の状態が変わることが良くありますので、妊娠は医師と相談してください。 病状が落ちついて時期の良いときに計画できるようしましょう。
(注)当院のホームページの解説よりも詳しいものが、ネット上でたくさんあります。そちらを参考にしてください。
「甲状腺機能亢進症&妊娠」 で検索してください。
2003.2.6記
A:甲状腺機能亢進症の約10%が無痛性甲状腺炎と呼ばれる病気です。バセドウ氏病と治療方法が異なるので両者を見極めることが大事です。
無痛性甲状腺炎は、自己免疫により甲状腺組織が破壊されて、中にあった甲状腺ホルモンが血液中に漏れることにより起こる甲状腺機能亢進症です。 比較的軽度の橋本氏病により生じると考えられています。甲状腺機能亢進状態は通常1〜3ヶ月間持続します。
甲状腺組織に蓄えられている甲状腺ホルモンは有限なので、長くても数ヶ月で血液中の甲状腺ホルモンは低下し、逆に甲状腺機能低下症の状態が、1〜数ヶ月持続します。
組織破壊は一時的で組織も回復してくるため、その後に甲状腺の機能は正常化します。
無痛性甲状腺炎は抗甲状腺薬は必要としません。動悸などの症状があるときは、甲状腺ホルモンの働きの一部を抑制するβ遮断薬を使います。
●バセドウ氏病との鑑別のポイント
【症状】
・甲状腺中毒症状がでてからの期間が短い。
・甲状腺中毒症状が比較的軽い。
・甲状腺腫が比較的軽度。
・バセドウ氏病の眼症状がない 。
【検査】
・TSH受容体抗体が陰性のことが多いが、絶対的ではない。
・ヨードまたはテクネシウム摂取率が低い 。
2003.2.1記
A:以下の様な場合に専門医への紹介を考慮します。
・ バセドウ氏病で眼球突出がある場合(治療が難しい場合が多い)。
・ バセドウ氏病が疑われるのに、TSHレセプター抗体が陰性の時 。
・ 妊娠しているバセドウ氏病。
・ 結節性の腫瘤を触れた場合は、できれば甲状腺専門の外科へ紹介。
・ 心不全や消化器症状などの症状が非常に強いバセドウ氏病の時 。
・ 薬による発疹、肝障害、白血球が大きく減少した場合(無顆粒球症)などの薬の副作用がでた時 。
・ 大量の薬を飲んでいるのに効かない時。
2003.2.1記