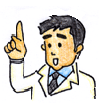
|
インフルエンザの追加情報(2)
|
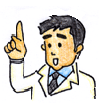 |
公開日2005.12.14 更新日2007.3.27 更新履歴 HOMEへ(メニューを表示) メニューを隠す
記事はあくまでも参考に留めてください。
流行状況(約2週間遅れ:【1】全国の集計、【2】各地の流行状況:インフルエンザ情報サービスより)
16)麻黄湯をタミフルと併用すると症状のある日数が短くなる 2005.11.16記 、2007.3.27一部修正
17)タミフル服用による小児死亡は、「明確な根拠なし」(米国FDA発) 2005.12.20記
18)B型インフルエンザへのタミフルの効果が小児で年々低下傾向 2005.12.20記
19)新型インフルエンザ対策行動計画では、現在の流行状況は「フェーズ3」 2005.12.20記
20)抗インフルエンザ薬の併用は有効か 2006.01.14記
21)症状のないインフルエンザ感染(不顕感染)はどのくらいあるのか 2006.03.08記
まとめ:タミフル単独よりもタミフルに麻黄湯を併用すると、頭痛と全身倦怠感の症状持続日数が短縮された。なお、麻黄湯は中枢神経系(脳)に作用するEphedraという成分が含まれているので、タミフル同様に異常行動には注意が必要と思う。
タミフル(一般名オセルタミビル)投与によって、有熱期間は短くなるが、早く解熱しても頭痛や筋肉痛、全身倦怠感が続くことが多い。今回、タミフルと麻黄湯の併用が、タミフル単独よりも症状の改善に有効かどうかを福富医院の福富 悌らが検討し、漢方薬の専門誌に報告した。
【対象】
2003年冬-2004年春の時期に臨床的にインフルエンザ、インフルエンザ様疾患と診断された症例とインフルエンザ迅速診断キットでインフルエンザと確認できずに風邪症候群として扱われた症例の一部。
|
タミフル単独群とタミフルと麻黄湯の併用群の有症状期間の比較
|
|||
|
インフルエンザ症例(インフルエンザ様症状で、診断キット陽性)での検討
|
|||
|
タミフル単独群
|
タミフルと麻黄湯の併用群
|
||
|
症例数
|
12例(男4、女8)
|
10例(男6、女4)
|
|
|
年齢
|
10-46歳(平均31.9±13.0)
|
15-47歳(平均33.6±10.4)
|
|
|
38℃以上の発熱日数
|
1.7±0.8日
|
1.9±0.6日
|
有意差なし |
|
頭痛の持続日数
|
2.4±1.0日
|
1.3±0.5日
|
有意差ありp=0.018 |
|
全身倦怠の持続日数
|
2.3±1.2日
|
1.3±0.5日
|
有意差ありp=0.179 |
|
風邪症候群(インフルエンザ様症状だが診断キット陰性)の症例での検討
|
|||
|
両群間で、発熱、頭痛、全身倦怠感の持続日数に差がなかった。
|
|||
参考
漢方医学Vol29,No.5 2005 p228 福富 悌ほか(福富医院)
2005.11.16記 2007.3.27修正
まとめ:2005年秋の日本小児感染症学会でタミフル服用後に死亡した12人の報告がなされ、新聞やテレビで「タミフルによる副作用である」と思わせるような報道が何度もあったが、タミフルの副作用による可能性は低い。
インフルエンザ治療薬のタミフル(商品名)の承認以来、同薬の服用後に死亡した16歳以下の患者が12人いる。この問題に関して、米食品医薬品局(FDA)小児科諮問委員会は11月18日、「現時点ではタミフルによる副作用が死因になったという証拠はない」との見解を示した。
この12症例は全員が日本人で、突然死4人、心肺停止4人、意識障害、肺炎、窒息、急性膵炎による心肺停止が各1人で、2-3歳児が最も多かった。
FDAはタミフル服用との因果関係を検討した。しかし、タミフル以外の薬剤も服用していたり、詳細な情報が不足する例があることや、タミフル非服用時にもインフルエンザによる突然死が報告されていることなどから、タミフル服用と死亡との因果関係の特定は困難だった。
一連の騒動に関して、インフルエンザ脳症に詳しい岡山大小児科教授の森島恒雄氏は、
(1)インフルエンザ罹患時の異常行動は、タミフルの発売以前から、インフルエンザ脳症の初発症状などとして数多く報告されている。
(2)タミフルがあまり使われていない米国でも、2003/04シーズンにインフルエンザに伴う小児の突然死が社会問題となった
(3) そもそもインフルエンザは軽い病気ではなく、幼児死亡は多い一一
という点を挙げ、医師に対して冷静な対応を呼びかけた。
ただし、日本でも引き続き学会レベルで同薬の副作用や耐性ウイルス発現状況の調査を行うべきであり、小児への使用に関しては、対象年齢を絞るなどの検討が必要であるとした。
【当院の意見】
タミフルが使われるようになってから、小児の死亡例が増えたわけでもなく、タミフルの副作用による死亡は、あまり考える必要はないようである。しかし、インフルエンザ脳症のようなインフルエンザの重症合併症にはタミフル単独治療では、十分な効果が得られず、早期のステロイド投与が必要なことを知っておくとよい。
【当院の意見】2007.03.26追加
2007.3月タミフルで10代の飛び降りなどの異常行動の報告が多いと言うことで、10代限って使用を控えるように指示がでた。タミフルがこれらの異常行動のすべての原因であるとは思わないが、異常行動が増加する危険性は否定できない。十分な調査報告を望む。
参考
日経メディカル2005年12月号 p38からの引用(一部改変)
2005.12.14記 2007.03.26修正
まとめ:小児での調査では、タミフルの効果はA型インフルエンザでは今のところ変化がないが、B型インフルエンザでは発売から4シーズンで早くも年々弱まる傾向にある。
「B型インフルエンザに対するタミフルの効果が、過去4シーズンで徐々に低下している」と第37回日本小児感染症学会で発表があった。小児科開業医の有志による研究結果で、藤原典博氏(ふじわら小児科内科医院)らは、2001/02シーズンから2004/05シーズンまでの過去4シーズンにわたって、迅速診断キットでインフルエンザと診断され、発症48時間以内にタミフルを5日間内服した小児のA型患者計1,516人、B型患者計926人について、解熱率や遷延再発熱の有無などを検討した。
各群の年齢や投与開始時期に差はなかった。
A型インフルエンザでは、過去4シーズンを通して、タミフル投与開始後48時間以内の解熱率が84-89%と良好だった。しかし、B型インフルエンザでは、2001/02シーズンの48時間以内の解熱率は83.3%だったが、その後、2002/03シーズン66.1%、2004/05シーズン57.7%と有意に低下していた。
|
B型インフルエンザに対するタミフルの効果の年次推移(藤原氏ら)
|
||||
|
観測時期
|
2001/02
|
2002/03
|
2003/04
|
2004/05
|
|
症例数
|
66人
|
247人
|
10人
|
603人
|
|
投与開始48時間以内
の解熱率 |
83.3%
|
66.1%
|
(約60%)
|
57.7%
|
|
治療抵抗例
|
6.1%
|
23%
|
(10%)
|
32%
|
さらに、治療抵抗例(有熱期間が72時間を超える遷延例+解熱後24時間以上を経た再発熱例)の頻度も、A型では2001/02シーズンから2004/05シーズンで3.2-4.5%だったが、B型では6.1%、23%、10%、32%と、症例が少なかった2003/04シーズンを除いて年々有意に増加していることが判明した。また、シーズン前のワクチン接種の有無で累積解熱率を比較したが、ワクチン接種による症状の軽減効果は認められなかった。藤原氏は「流行株の変異により、タミフルに対するB型インフルエンザウイルスの感受性が低下していることが考えられる。今後、B型に対しては、タミフルの投与量の増量や異なる抗ウイルス薬の選択など、新しいアプローチの検討が必要だ」と話しているという。
【当院の意見】
B型インフルエンザに対する既存のワクチンは効果が弱いと報告されている。さらに、インフルエンザ治療薬であるタミフルも有効率が年々低下しているという。どういうメカニズムによるのかも含めて、タミフルに頼り切った現在の日本でのインフルエンザ治療方針を再考した方が良さそうである。当院では、中学生以上の年齢でB型インフルエンザになった場合は、吸入薬であるリレンザを今後は第一候補にしたいと思っている。また、漢方薬の麻黄湯との併用も積極的に行いたいと考えている。
参考
日経メディカル2005年12月号 p38-39からの引用(一部改変)
2005.12.14記 2005.12.20修正
まとめ:新型インフルエンザの出現とその世界的な大流行の危険性が、政治的にも問題視されるようになってきた。
2004年、20005年と2年続けて、世界的なトリインフルエンザの感染拡大に伴って、インフルエンザの世界的大流行(ハンデミック)発生が現実味を帯びてきた。このことが報道でも大きく取り上げられるようになった。東南アジアではヒトヘの感染例が増えて、2003年12月以降で125人に上り、計64人の死者が出ている(2005年11月10日現在)。こうした事情を踏まえて、厚生労働省は2005年11月に
「新型インフルエンザ対策行動計画」を公表した。流行状況をフェーズ1-6に分類し、フェーズ別の対策を打ち出している。
現在は「フェーズ3」の段階であると認識
厚生労働省は全人口の25%が新型インフルエンザに罹患すると仮定し、医療機関を受診する患者は最大2500万人、死亡者は最悪で64万人に上ると推計している。現在の段階は「フェーズ3」で、経口抗インフルエンザ薬のタミフル2500万人分を備蓄する方針である。また、H5N1型の鳥インフルエンザを基に開発したワクチンの臨床試験は来年初めに着手、来秋の承認申請を目指している。
しかし、 この行動計画はあまいとの批判も多い。「タミフルの備蓄は2500万人分では不足」(横浜市西区のけいゆう病院小児科部長の菅谷憲夫氏)、「新型の治療を優先するため、『新型インフルエンザの疑い患者以外には、抗ウイルス薬の使用を控えるよう指導jとあるが、新型か従来型かの区別はできない」(東京都老人医療センター感染科症区長の増田義重氏)、など。
|
「新型インフルエンザ対策行動計画」の概要
|
||
| フェーズ1 | ヒトへ感染する可能性を持つウイルスが動物に検出 | |
| フェーズ2 | 動物からヒトヘ感染するリスクが高いウイルスが動物に検出 | 国内非発生 |
| 国内発生 | ||
| フェーズ3 | ヒトヘの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認 (ヒトヒト感染は基本的にない) |
国内非発生※ |
| 国内発生 | ||
| フェーズ4 | ヒトからヒトヘの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認 (感染集団は小さく限られている) |
国内非発生 |
| 国内発生※ | ||
| フェーズ5 | ヒトからヒトヘの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認、大きな集団発生(ハンデミックのリスク高まる) | 国内非発生 |
| 国内発生 | ||
| フェーズ6 | ハンデミックが発生し、世界の一般社会で急速に感染が拡大 | 国内非発生 |
| 国内発生 | ||
| フェーズ3: ※国内非発生時の対策 |
| ○海外渡航者への注意喚起 ○プロトタイプワクチン(H5N1型鳥インフルエンザを基にしたもの)原液の製造・貯留 ○タミフル2500万人分備蓄 ○指定医療機関の整備、など |
| フェーズ4: ※国内発生時の対策 |
| ○発生地域での大規模集会などの自粛勧告 ○患者を診景した医療従事者へのタミフルなどの予防投与 ○新型インフルエンザワクチンが生産され次第、希望者に接種 ○新型インフルエンザ疑い患者には入院勧告 ○新型インフルエンザ疑い患者以外には、抗ウイルス薬の使用を控えるよう指導〔不足が予測される場合〕、など |
【当院の意見】
この行動計画の予想は非常に甘い。社会的パニックを起こさないように、意図的に甘く予想していると考えられる。「死亡リスクも高い新型インフルエンザの大流行ともなれば、多数の患者やその近辺の発症前の人も受診するだろう。また、タミフルの予防的使用によりその需要は飛躍的に増加するものと思われる。同一人物が、数回タミフルを服用することも多くなり、2,500万人分のタミフルの備蓄では社会的パニック状態になると予想される。
ただし、タミフルによりインフルエンザの重症例が救えるかどうかは大変疑問である。現在でもタミフルは症状の発現を短くするだけで、肺炎や小児の脳症などの重症合併症を減らすとの報告はない。
なお、新型インフルエンザのハンデミックの危険性はこれまで幾度となく指摘されてきた。2005年にパンデミックが起こる可能性が急に高くなったわけではないと思うのだが、いずれ来るだろう新型インフルエンザの世界的な対策は今から考えておいても早すぎることはない。
参考
日経メディカル2005年12月号 p63からの引用(一部改変)
2005.12.14記 2005.12.20修正
まとめ:現在ある3種類の抗インフルエンザ薬のうち、A型インフルエンザには「タミフルとアマンタジンの併用」が有用。
インフルエンザ診断キットによりインフルエンザと診断された患者を対象に、抗インフルエンザ薬の(1)アマンタジン=商品名シンメトレル、アマゾロンンなど、(2)オセルタミビル=商品名タミフル、(3)ザナビル=商品名リレンザの単独治療と併用治療の効果を比較した臨床研究の発表があった。第一線でインフルエンザの治療を行う診療所の外来にとって大変有用な情報であるので、その要約を一部紹介する。
◆検討-1◆
【対象】
2001-2002年インフルエンザ診断キットによりA型インフルエンザと診断された患者94例
【目的】
・オセルタミビル150mgとアマンタジンン100mgまたは50mgの併用効果があるか?
・試験管内(in vitro)での資料では、タミフルはアマンタジンの1000-2000倍以上の効果があるとされているが、実際の診療でも治療効果に差があるのか?
・マクロライドの併用は効果があるのか?
【効果判定方法】
解熱までの時間、鎮咳効果、副作用
【結果】
・オセルタミビル150mgまたは75mgとアマンタジン100mgの単独治療では治療効果に差がなかった。薬価が9.5倍(後発品を使うとさらに安い)あることを考慮するとアマンタジンも有力な選択枝となる。
・マクロライドの併用は鎮咳効果がわずかにみられた。
・オセルタミビルとアマンタジンの併用は著しく効果が高く、単独治療よりも約7時間早く解熱した。この時のアマンタジン50mgと100mgの差はわずかであった。
・ザナビルは解熱までの時間が長く、インフルエンザ迅速診断キットの陽性時間が長く続いた。また、軽い喘息発作が3例(29例中)にみられた。
・副作用はアマンタジンでふらつき、オセルタミビルで下痢がみられた。
また、発表者はトリインフルエンザの治療に関して、次のような内容のコメントを述べている。
--- 鳥インフルエンザH5N1では40例中32例の致死率である。アマンタジンの効果がなく(耐性)、オセルタミビルの効果もはっきりしない。ザナビルとオセルタミビルの併用を考慮したほうがよい ---と。
【当院の意見】
この報告をもとにすると、インフルエンザA型でもっとも勧められる抗インフルエンザ薬は、「常用量の半量のタミフル75mg+アマンタジン100mg」
である。単独の使用なら、タミフル150mgとアマンタジン100mgの効果に差がない。リレンザ単独はタミフル単独よりも効果が劣る。ということになる。以上のことを踏まえて今後のインフルエンザ治療を行いたい。ただし、同様の薬剤の併用療法は保険診療請求で認めれないとされる可能性が大きいので、上記の結果をそのまま診療の基準にすることはできない。
【当院の意見】追記
2006年1月の新しい報告によると、2005年末に検出されたA型インフルエンザウイルスのアマンタジン耐性が異常に多いとの報告があった。2006年2月現在、アマンタジンの使用は無効の可能性が高いので、使用していない。
まとめ:状況によって異なるが、典型的なインフルエンザ症状は約50%だったという報告がある。
以下参考資料のまとめ
インフルエンザウイルスそのものに反応して検査できる迅速診断キットが普及してきたために、インフルエンザの症状にはごく軽症から重篤なものまで多彩であることがわかってきた。その中で発病しない症例の存在も判明した。通常レベルの流行時におけるA型インフルエンザ感染者の中で、50%が典型的インフルエンザの症状、30%程度が風邪様症状(上気道症状)、20%程度が無症状(不顕性感染)とする報告がある。本邦では、約6%の不顕性感染があったとの報告がある。B型インフルエンザについての詳細な報告は見当たらない。このように不顕性感染があることは以前から知られている。不顕性感染の報告に数%から20%と開きがあるが、調査法やそのときの流行規模やその時点での免疫抗体の保有率の違いもあるためと考えられる。一般的には抗体の保有率が高いほど不顕性感染の頻度が増加すると推測される。
【当院の意見】
症状のない、または症状がとても軽いインフルエンザ感染がどれほどあるのかは、なかなか知ることが難しい 。結構あるように思うのだが、結核などの重症感染とは違い、これらは治療の必要性が高くないので臨床的にも大きな問題とならない。高齢の患者さんでワクチンをうつようになってから風邪を引かなくなったという人も少なくない。これも風邪に混じって、軽症インフルエンザが存在する証なのか?
参考
日本医事新報 2005年07月02日号 p92-93 「インフルエンザB型流行時の迅速診断の実際と不顕性感染」久留米大医療センターリウマチ・膠原病センター講師 加地正英
2006.03.08記 2006.03.10修正