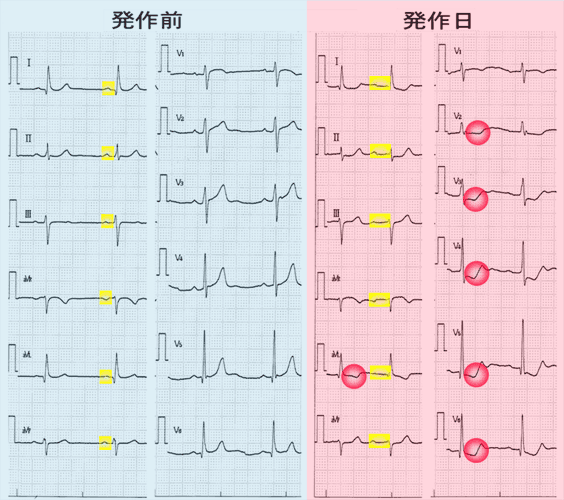
■■ 右冠動脈(近位部:1番)閉塞による急性心筋梗塞 ■■
公開日 2004.04.18 更新日2004.04.18 更新履歴
HOMEへ 左メニューを隠す
【心電図検査】心電図を拡大する
左は発作前、右は発作時の心電図。
発作時の心電図はST低下のみで、ST上昇はなかった(赤色の目印)。PQ延長(黄色の目印)が見られた。側副血行が発達していたために、完全な血流遮断が起こらず、ST上昇が生じなかったと冠動脈造影を行って分かった。
心電図は簡単にできる検査なので、急性心筋梗塞を疑ったら、まず真っ先に行う検査です。典型的な急性心筋梗塞の心電図所見ではST上昇がおこりますが、小さな枝、左回旋枝や左冠動脈主幹部、側副血行が発達している場合などは、ST低下ばかりでST上昇がないこともあります。胸部や上腹部症状があり、前回に比べて心電図でSTまたはT波の変化があれば、狭心症発作・急性心筋梗塞や低酸素血症(肺塞栓症、心不全、喘息、肺炎など)を疑ってください。
ただし、急性心筋梗塞発症の数時間の超急性期では、ときにST上昇がわかりにくい(超急性期の心電図)こともあり、1回の心電図のみで確定するのは困難です。
これらの場合は心エコー検査が威力を発揮します。
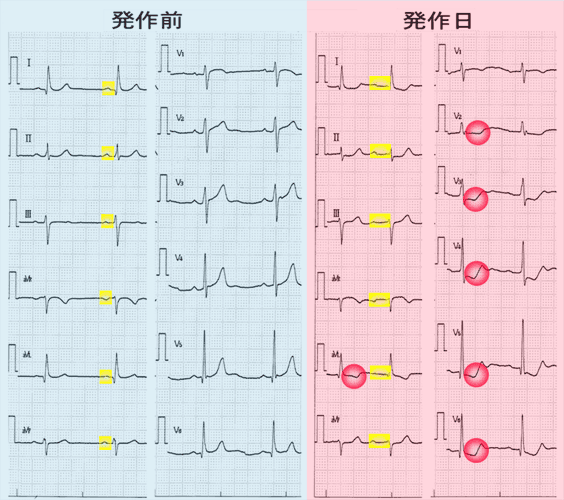 |