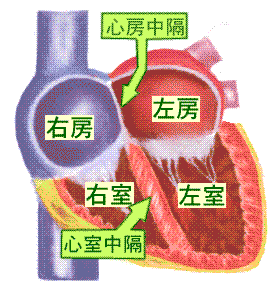
左右の心房と左右の心室の 各部屋は筋肉の壁によってできており、筋肉の収縮と弛緩により、周期的に大きくなったり、小さくなったりする。しかし、心臓の弁がないと血液は行ったり来たりするだけで、前へ進まない。 心臓の弁は、閉じたり開いたりして、血液の流れを一方向にしか流れないようにしている。
|
【心臓弁膜症とは】
|
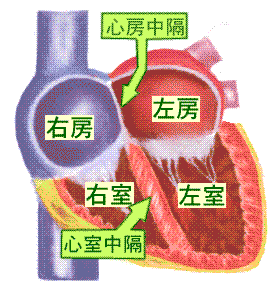 |
心臓の弁膜は心臓の内面を覆う内膜が伸びてひだ状になってできたもので、左右の心室の入口と出口のところにある。 左右の心房と左右の心室の 各部屋は筋肉の壁によってできており、筋肉の収縮と弛緩により、周期的に大きくなったり、小さくなったりする。しかし、心臓の弁がないと血液は行ったり来たりするだけで、前へ進まない。 心臓の弁は、閉じたり開いたりして、血液の流れを一方向にしか流れないようにしている。 |
| 心臓には四つの部屋があり、左右の部屋は心房中隔と心室中隔という筋肉や線維膜の隔壁で隔てられている( 図1)。 |
酸素が少なくなった静脈血(皮膚を透かしてみると暗い紫色の血液)が、全身から右心房に戻り、右心室へ送られて、右室の収縮により肺に押し出される。血液は肺で酸素を受け取り、酸素を多く含んだ動脈血(皮膚を透かしてみると鮮紅色の血液)となり、左心房に戻り、左心室に送られる。左心室は四つの部屋の中で、最も力強い収縮で、全身の動脈に血液を送り出す。
|
全
身 の 静 脈 → |
右
心 房 → |
三
尖 弁 |
右
室 → |
肺
動 脈 弁 |
肺
動 脈 → |
肺
の 毛 細 血 管 → |
肺
静 脈 → |
左
房 → |
僧
帽 弁 |
左
室 → |
大
動 脈 弁 |
大
動 脈 → |
動
脈 → |
体
中 の 毛 細 血 管 → |
|
|
血液中の酸素が少ない静脈血
|
血液中の酸素が多い動脈血
|
||||||||||||||
心臓には、左心房と左心室の間にある僧帽弁と、左心室の出口にある大動脈弁、右心房と右心室の間にある三尖弁と、右心室の出口にある肺動脈弁の四つの弁がある。僧帽弁は二枚の弁尖(べんせん)、他の心臓弁は三枚の弁尖でできている。心臓弁の異常によっておこる疾患を心臓弁膜症と呼んでいます。弁の開放が不十分で、弁口が狭い場合を「弁狭窄」、逆に弁の閉鎖が不完全で逆流する場合を「弁逆流」または「弁閉鎖不全」と呼んでいる。
小児の弁膜症は先天性が多く、成人の弁膜症は後天性が多いため、弁膜症の好発部位に違いがある。成人では僧帽弁膜症と大動脈弁膜症が多く、肺動脈弁や三尖弁の弁膜症が一次的に生じることはめったにない。さらに高齢者では、これらの弁膜症、心房細動、心不全に三尖弁閉鎖不全を合併することがよくある。
弁膜症の病態は、弁の開放制限による狭窄と閉鎖不全による逆流があり、両者が併存することも少なくないが、どちらかが優位なことが多く、それぞれに応じた治療が必要となる.
従来、心臓弁膜症は僧帽弁のリウマチ性弁膜症が主体でしたが、現在では栄養状態の改善、抗菌薬の汎用によって新規のリウマチ性弁膜症は減少し、高齢者にのみリウマチ性弁膜症を認めることが多くなった。
一方、人口の高齢化によって、高齢者の動脈硬化性ないしは退行性変性と考えられる大動脈弁狭窄症が増加している。僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症も、リウマチ性病変は減少し、弁逸脱(弁の尖端の接合がずれること)ないしは変性によるものが主体となっている。